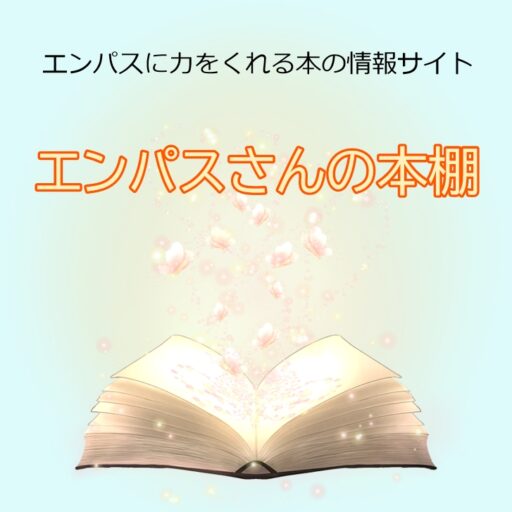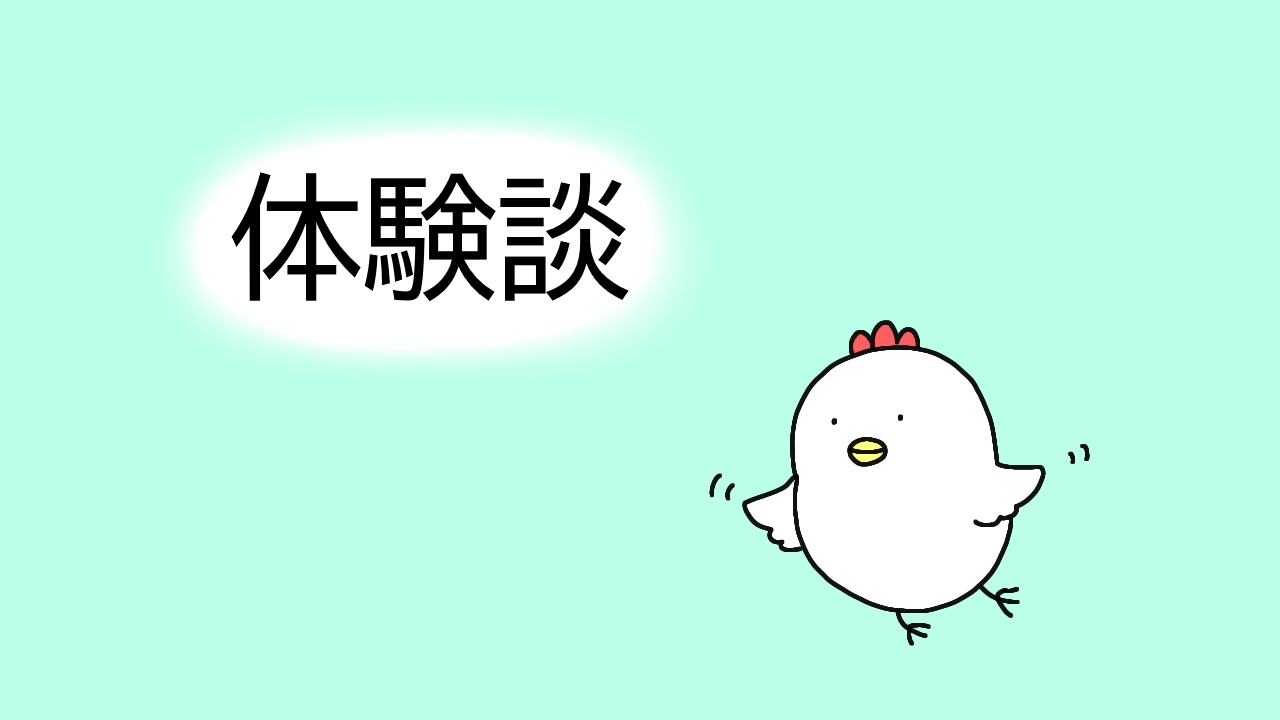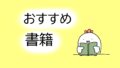2.いったん母から離れる
離れる=見捨てるではない
次に行うことは、いったん母から離れるということです。
ここで大事なのは、決して母親を実際に見捨てるわけではないことです。
母親にいずれ助けが必要になった場合には、介護などの現実的な問題に向き合えばいい。
0~2のプロセスを経ることで、自分の子どもを育てるために、そして自分の人生を生きるためには、今はいったん母親から心理的に離れなければいけないことがわかってくると思います。

私の場合は、母の存在により自分の育児に支障が出るのが明らかだったので、何とかしなくてはならないと考えました。
母親と心理的に離れるために
可能なら物理的に距離をとる
0~2のプロセスを経ることは成長のために大切なことでしたが、心にはけっこうな負担があると思います。癒されるためには時間が必要であって、この期間に母親と会うことによりさらに混乱する場合があるので、可能であれば物理的に距離をとることを一番お勧めします。
具体的な境界をひく
物理的に距離が取れない場合は、母親と会った時にどんなことで傷つくのか、どんなことをやめてほしいのかを分析し、それを母親に伝える方法があります。
私の場合は、「自分の問題を私に相談すること」を真っ先にやめてもらいました。具体的には、姉やその子供達についての困った行動を私に相談する(愚痴を言う)ことをやめてもらいました。
口頭ではすぐに忘れられてしまう可能性があるので、手紙にし、守ってもらえない場合は「自分の子どもの健全な成長のために」やむを得ず会えなくなる旨も伝えました。
孫に会えないことは母にとって何より辛いことのようなので、母は私の要求をのんでくれました。日によって程度はありますが、今は節度ある関係をもつことができています。
「礼節ある関係」をめざす
プロセス1でも登場した、キャリルマクブライト著「毒になる母」には、めざすべき母親との関係について記してあります。
私たちがめざすのは、母親との「礼節ある関係」です。
接触するときはあくまでも軽く礼儀正しい関係を保ち、心のふれあいを求めない。これは母親との関係をあきらめたくはないが、母親らしい言動を期待しない娘にとって最良の方法だ。
キャリル・マクブライト著 江口泰子訳 「毒になる母–自己愛マザーに苦しむ子供」講談社 🅿222より引用
罪悪感にのみこまれないで
自己愛の強い母に育てられた娘がこのように母親と距離を置こうとするとき、罪悪感に苦しめられると思います。(本当に多くの書籍にこのことが書いてあります)
ただ、自分の家庭を幸せなものにするため、負の連鎖を受け継がないためには避けては通れない段階になるので、ぜひ行ってみることをお勧めします。